税とは何か?国家を支える「見えないインフラ」

国にとって「税」は、単なる財源ではありません。
税は、社会のインフラを支え、国民の暮らしを保障し、国家運営の根幹を成す、極めて重要な制度です。道路や学校、警察、医療、福祉といった公共サービスはすべて税によって成り立っており、国民が税を負担し合うことで、社会の安定と発展が支えられています。
明治時代、数百年続いた江戸時代が終わり、新しい国のあり方を示す「大日本帝国憲法」が1889年に発布されました。しかし、それに先立つ2年前の1887年には、当時の日本にとっては新しい税であった所得税が導入されています。つまり、憲法より先に所得に課税される税の制度がつくられたのです。それほど、国を支える仕組みとして税は重要な存在といえます。
さらに、税は、国家と国民との間の契約ともいえる存在であり、民主主義国家においては、とりわけ重要な制度です。
日本では、かつては国が税額を決めて通知する「賦課課税制度」が一般的に採用されていましたが、第二次世界大戦後、納税者が自ら計算して申告する「申告納税制度」中心の申告制度へと転換されたことで、納税に対する国民の自主性と責任が一層重視されるようになりました。
しかし、税法や税制は、経済活動の複雑化・国際化に伴って、年々専門化しています。こうした状況において、全ての納税者が正確に税制を理解し、正しい納税を行うことは容易ではありません。
そこで、税の専門家として、納税者を支援し、正しい申告と適正な納税を支援する存在が「税理士」です。税理士は、単に税務手続きを代行するだけでなく、納税という国を支える仕組みにおいて、国家と国民を結ぶ懸け橋の役割を担っています。
税理士とは?国家資格の専門家が担う使命

税理士は、税理士法に基づいて定められた国家資格であり、税務の専門家です。法人・個人を問わず、納税者に対して税務に関する代理、書類の作成、相談といったサービスを提供しています。これらはすべて、税理士のみが行うことのできる「無償独占業務」とされており、無資格者は、報酬の有無にかかわらず行うことはできません。
税理士法第1条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と明記されています。
法律上「独立した公正な立場」とされているのは、納税者の代理人ではあるが、あくまで中立な立場として、法律に従って、その権利を保護し、正しい義務の履行を支援することが求められているからです。
税の徴収には、国が国民の財産の一部を強制的に国家の手に移すという側面があります。
国と、一個人である納税者の間には、その権限や税に対する知見に大きな不均衡があることが通常ですが、専門家である税理士が公正な立場から、法律に基づいた適正な納税を支援することで納税者の権利が守られているのです。
出典:e-Gov「税理士法第一条 税理士の使命」
税理士の業務とは?3つの独占業務

税理士の独占業務には、以下の3つがあります。
| 税務代理 | 確定申告書や修正申告書の提出、税務調査の立会い、異議申し立てなど、税務に関する手続きを納税者に代わって行う業務です。 |
|---|---|
| 税務書類の作成 | 法人税、所得税、消費税などの各種税務申告書や届出書を作成します。これらは正確性が強く求められる書類であり、専門的知識なしには作成が難しいものです。 |
| 税務相談 | クライアントからの税金に関する個別・具体的な相談に応じ、法令に基づいた助言を行います。例えば、税額のシミュレーションや、決算対策の相談などが該当します。 |
これらの独占業務以外にも、税理士は、補助金の申請支援、資金繰り支援、事業承継、M&A、経営計画の策定など、経営に関わる業務に多岐に対応しています。
これらは税理士の独占業務ではありませんが、税や会計と密接に関連する分野であり、その知識が活きる場面が多いため、税理士が活躍する機会が多くあります。
そのため、税理士は「経営者の最も身近な相談相手」ともいわれています。
税理士制度の歴史 シャウプ勧告から現代へ
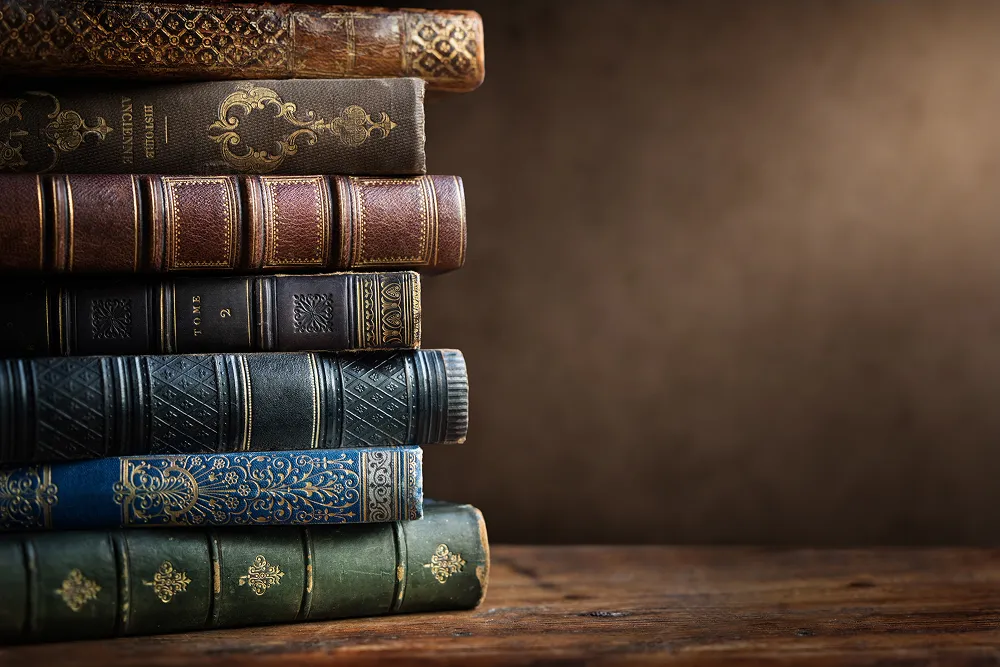
日本の税理士制度のルーツをたどると、戦前、一般的に行われていた「賦課課税」による納税の制度まで遡ります。この制度では、税務当局が納税額を決定し、納税者に通知するという仕組みがとられていました。
しかし、日清・日露戦争を経て、それまでの地租中心から、商工業者にも税負担を求める税制に移行していく中で、納税者自身だけでは納税の手続きを行うことが難しくなっていきます。
そこで、戦時中の1942年、税務書類の作成や手続きを代行する「税務代理士」という職業が誕生しました。これが現在の税理士のルーツです。
戦後、日本は連合国の占領下になり、各制度の民主化が進められました。税制も例外ではなく、1949年にアメリカの経済学者カール・シャウプ博士を団長とする「シャウプ使節団」が来日し、戦後税制改革の青写真を提示します。ここで打ち出されたのが、現在の申告納税制度の原型です。これは、納税者自らが課税標準や税額を計算し、申告する制度であり、納税者と国家との「相互信頼」が前提となっています。
とはいえ、戦後直後の混乱期においては、納税者が自ら税法を理解し、正しく申告することは困難でした。また、それを導く税務行政側の体制も十分には整っていませんでした。
このため、税務代理士の制度では申告納税制度を中心とした納税者の支援には、不十分とされ、より高い専門性を備えた税の専門家が必要となり、1951年に「税理士法」が制定、現在の「税理士」制度が誕生することとなったのです。それ以来、税理士は、税の専門家として、わが国の申告納税制度を支える存在であり続けています。
近年では、資産税、国際税務、組織再編などの分野で、専門的に対応する税理士も増えており、単なる記帳代行業務にとどまらない、知的専門職としての地位を確立しています。
なお、2001年には、税理士法人制度が創設され、複数の税理士が法人格を持って事業を展開できるようになりました。個人事務所中心だった税理士業界に、組織化・法人化という選択肢が加わったことで、現在では、グローバル規模の案件や、専門領域の分業などにも対応できるようになっています。
海外における税理士制度との比較

日本の税理士制度の特徴は、「税務に関する業務を無償・有償を問わず独占的に担える」という点にあります。実は、これは世界的にみても珍しい制度です。ドイツと韓国は、日本と同様に「税務代理・税務相談」を無償独占業務として定めている国ですが、言い換えれば、同様の制度は、この2ヵ国しかありません。
例えば、米国には「EA(Enrolled Agent)」や「USCPA」など、税務を扱う資格が複数ありますが、いずれも税務業務の独占権は持っておらず、弁護士や税務コンサルタントなどと競合する形で運用されています。
また、オーストラリアでは「有償」の場合に限って税務業務に制限が設けられていますが、無償であれば非有資格者でも税務相談などが可能とされています。
なお、類似する制度を持つ2ヵ国においても、日本とまったく同じというわけではありません、ドイツの税理士(Steuerberater)は、日本と同様に独立性を重視した専門家ですが、大きな違いは「税務訴訟の代理権」を有している点です。
納税者の代理人として、税務訴訟に出廷することが可能であり、より強い「権利保護者」としての役割を担っています。
また、韓国の「税務士」は、その使命に「納税者の権益保護」という文言を明記しており、日本以上に納税者側への立場が明確に打ち出されています。
こうした比較から見えてくるのは、日本の税理士は国家によって保護された資格であると同時に、公正な立場から申告納税を支援する専門家としての責任や信頼性が、非常に重視されているという点です。
出典:名古屋成年税理士連盟「ドイツ・韓国と比較した日本の税理士制度の検討」
税理士制度の将来像

近年、「AIに奪われる職業」として税理士がしばしば挙
げられることがあります。確かにAIやクラウド会計ソフトの進化により、領収書の読み取り、記帳代行、帳簿の突合、申告書の作成といった定型的・反復的な業務の自動化は、急速に進んでいます。
しかし、税理士にとって、これは危機ではなく「役割の進化」とも考えられます。AIが基礎的な定型業務を代替することで、税理士は、より戦略的・高付加価値な業務にリソースを割くことができます。
極めて専門性が高く、 AIでは代替しきれない税理士の介在が不可欠な分野をいくつか紹介します。
国際税務の複雑性
企業の海外進出やクロスボーダー取引の増加に伴い、移転価格税制やPE(恒久的施設)認定、タックスヘイブン対策税制(CFCルール)など、国際税務の論点は多岐にわたります。
海外子会社が日本企業の実質的な業務拠点と認定されてしまえば、国内課税リスクが生じ、過少資本税制などとの複合的な評価も必要です。こうした国際課税の適正化には、税理士による綿密な事前対策だけでなく、当局との交渉といった、いわば「アナログ」なスキルも求められます。
資産税の実務と資産構成の多様化
高齢化社会の進行や、基礎控除の引き下げ等の影響により、相続税の申告件数は年々増加していますが、被相続人の財産構成も複雑化しています。
不動産の共有持分、上場株・非上場株の混在、国外資産の存在、信託を活用した資産保全など、多様な構成要素が絡む申告の増加により、、財産の評価に関して高度な知識と実務経験が必要となる事案が増えています。
例えば、非上場会社の株式評価では、類似業種比準方式や純資産価額方式の選択、役員報酬の妥当性評価等様々な要素が評価に影響するため、専門のノウハウや経験が求められ、類型的な会計知識のみでは対応できません。
事業承継支援における法務・財務・税務の統合
事業承継では、単に贈与税・相続税の申告にとどまらず、後継者育成や組織再編、信託活用、株主構成の整理、関係者の合意形成など、多角的な検討が必要です。
例えば、相続人に種類株式を移転し、議決権を持たせない設計や、民法の遺留分侵害額請求への対策など、法務と税務、経営の交錯点での判断が要求されます。これらを総合的な視点で支援できるのは、税務と経営に精通した税理士ならではの役割です。
中長期的な経営戦略の立案支援、AIの分析を基にした人間によるリスク判断と戦略的アドバイス、個別具体性の高い案件に対する判断と助言、相続や事業承継における家族関係や感情に配慮した調整力などは、AIが代替しきれない高度な専門性、折衝力、倫理観、判断力が求められます。
むしろAIが普及するからこそ、税理士は、税務代理や書類作成にとどまらず、データで測れない要素をどう扱い、経営者を支援していくかが問われていくといえるでしょう。
なお、税理士自身のキャリアの多様化も進んでいます。かつては「事務所で修行→独立開業」という流れが主流でしたが、近年は大型税理士法人の所属税理士や、事業会社の社内税理士、教育者、スタートアップ経営者など、資格の使い方が多様になっています。
税理士制度の課題と展望

税理士制度は、創設から70年以上が経過しており、現代のビジネス環境に合わせた見直しが必要な部分もあります。また、社会環境の変化などにより、対応が必須な点も少なくありません。例えば、以下のような点について、税理士は考えていかなければなりません。
- 税制の複雑化と高度化
- 税理士の高齢化
- 他の専門家との協働
- 時代に合わせた制度のアップデート
それぞれについて、説明します。
税制の複雑化と高度化
経済環境の複雑化・国際化に加えて、政府による様々な租税特別措置の導入もあり、税制も高度化の一途をたどっています。国際課税やデジタル課税など、新たな論点が次々と生まれる中で、税制は今後さらに複雑になっていくでしょう。
こうした状況では、ひとりの税理士がすべての課税実務に精通するのは現実的ではありません。
そのため、今後は、専門家の集団による分業体制への移行が進むことが予想されます。
例えば、国際税務チームに移転価格、CFCルールなどの各テーマの専門家を配置したり、資産税チームに土地評価・不動産鑑定などの専門家を取り込んだりといった、複合型アプローチが増えていくと予想されます。
近年の税理士法人への集約化、税理士法人の大型化も、こうした背景を受けてのことだと思われます。
また、業務が高度化すればするほど、どれだけ専門家がそろっていたとしても、損害賠償リスクを完全に排除することはできません。
そこで、業務範囲や責任を明確化する業務委託契約書の整備や、最悪の事態に備える税理士職業賠償責任保険への加入などが、これまで以上に重要性を持つようになります。
AIと人間のダブルチェック体制の導入も、有効かもしれません。
税理士の高齢化
2020年の国勢調査によれば、税理士の年代別の就業者数の割合は以下のようになっています。
|
年代 |
割合 |
|---|---|
| 20代 | 2.19% |
| 30代 | 8.29% |
| 40代 | 20.56% |
| 50代 | 17.56% |
| 60代 | 25.14% |
| 70代 | 20.44% |
| 80代以上 | 5.84% |
60代以上の割合が過半数を占め、30代以下は1割にも満たない状況です。
受験資格の緩和などにより、ここ数年、税理士試験の受験者数は増加トレンドにありますが、業界として、若年層の呼び込みと若手の育成が、引き続き重要なテーマとなっています。
業界全体としても、それぞれの税理士や税理士法人としても、税理士の魅力発信、採用ルートの多様化、若手人材の育成支援などに取り組んでいく必要があるでしょう。
他の専門家との協働
昨今、税理士の業務領域は、記帳代行や税金の計算にとどまらず、経営アドバイザリー、M&A支援、国際業務など、多岐にわたっています。それに従って、公認会計士、弁護士、その他の専門家と職能が重なり合うことも格段に増えています。
そうした状況のもと、他の専門家との共存と競合のバランスが求められます。
他の士業者や専門家らと共存する上では、税理士としては、例えば、以下のようなアプローチが考えられるでしょう。
- チームアプローチ:案件ごとに最適な専門家(税理、会計、法務、ファイナンス)を配置し、相補的に動く
- 専門特化と差別化:税理士法人として、相続税高度専門、国際税務中心など明確な専門ブランドを構築する
- 連携によるスケールアップ:弁護士・公認会計士などとの共同案件についての定型契約を整備し、業務単価と価値水準を維持する
いずれにせよ、税制や法制が高度化する時代においては、様々な分野のスペシャリストが協働して、高い付加価値を提供するサービスが求められます。
これからの税理士は、どれだけ幅広いネットワークを構築し、クライアントに価値提供できるかが鍵となるでしょう。
時代に合わせた制度のアップデート
経済のグローバル化が進む中で問題視されているのが、税理士資格の国際的な取り扱いです。
例えば、日本の税理士が海外に移住したり、国外に長期駐在して国際的な税務業務に携わったりする場合、現行制度では税理士登録をいったん抹消し、帰国時に再登録せざるを得ません。
その間は、業務にあたって税理士を名乗れないことになり、国境を越えて活躍する専門家にとって大きな障害となっています。
また、税理士法人制度を巡っては、パートナー税理士全員に限度額を設けない「無限連帯責任」が負わされています。
税理士法人の制度導入時には想定し得なかった税理士法人の大型化が進み、グローバル企業の税務支援を行うことも珍しくない中で、一個人に見合わないリスクを背負わされているのが実情です。
今後、国際的な視野での柔軟な対応、税理士法人制度の見直しを含め、税理士制度自体の設計のリニューアルが求められる時期に来ているといえるでしょう。
おわりに

税理士は、単なる「税金の専門家」ではなく、納税者と国家の信頼関係を支える存在です。高度な専門性と倫理観が求められる国家資格でありながら、今や経営支援、ライフプラン設計、国際業務に至るまでそのフィールドは広がっています。
情報社会化や国際化といった変化は、税理士にとって脅威ではなく、進化のチャンスです。これらの変化に対応し、使命感と柔軟性を持ってクライアントに高い付加価値を提供し、時代をリードしていく税理士が、今後ますます求められていくでしょう。









